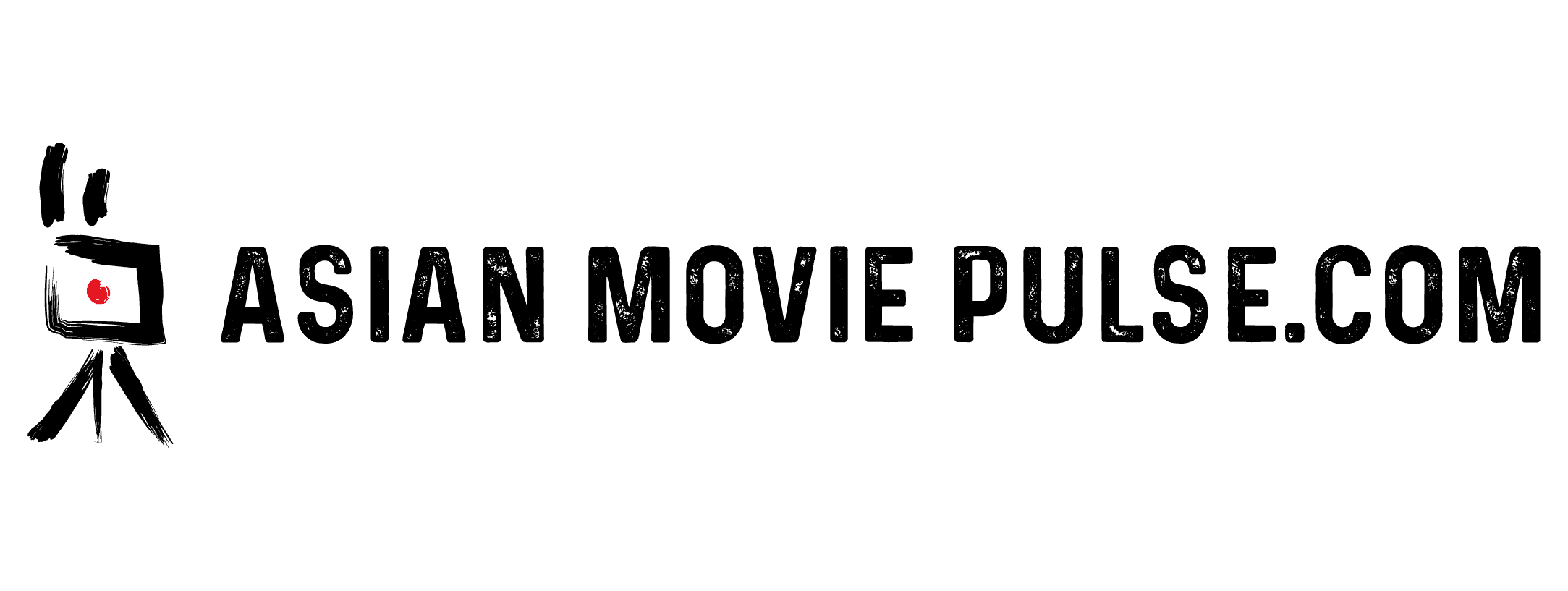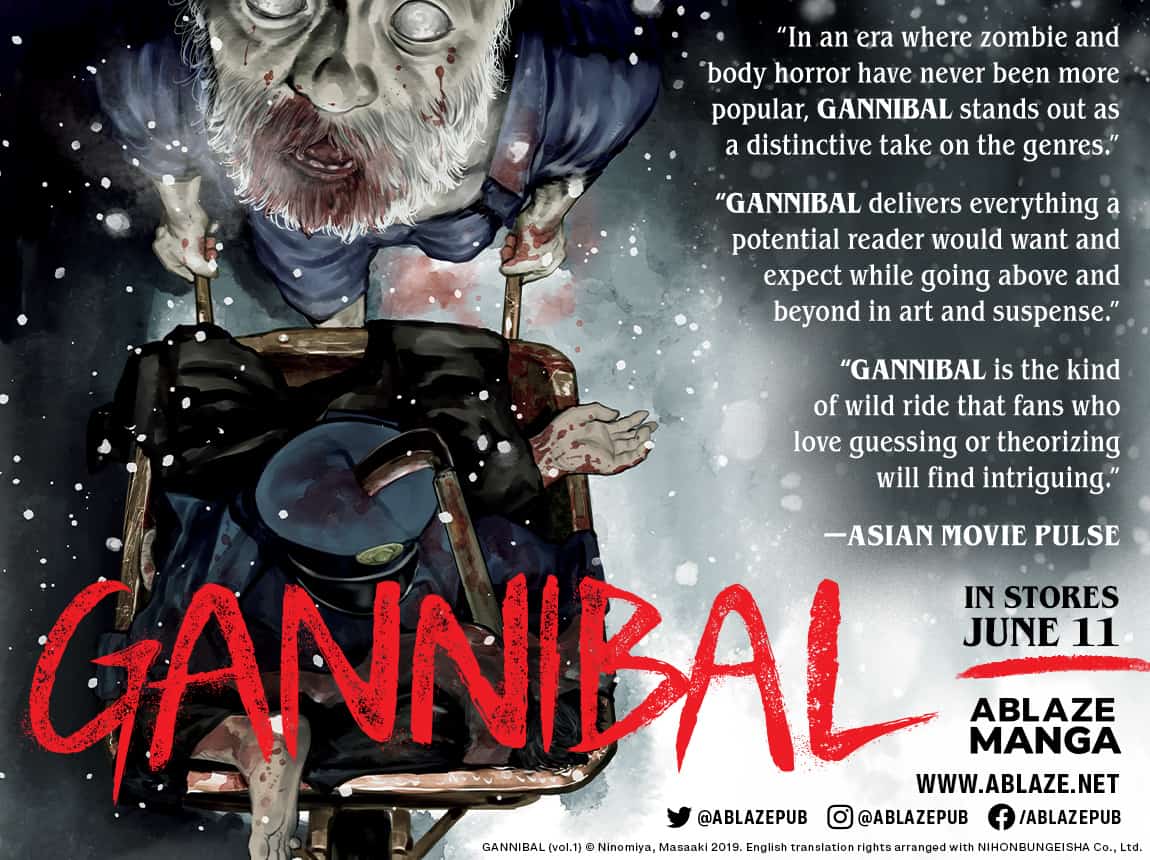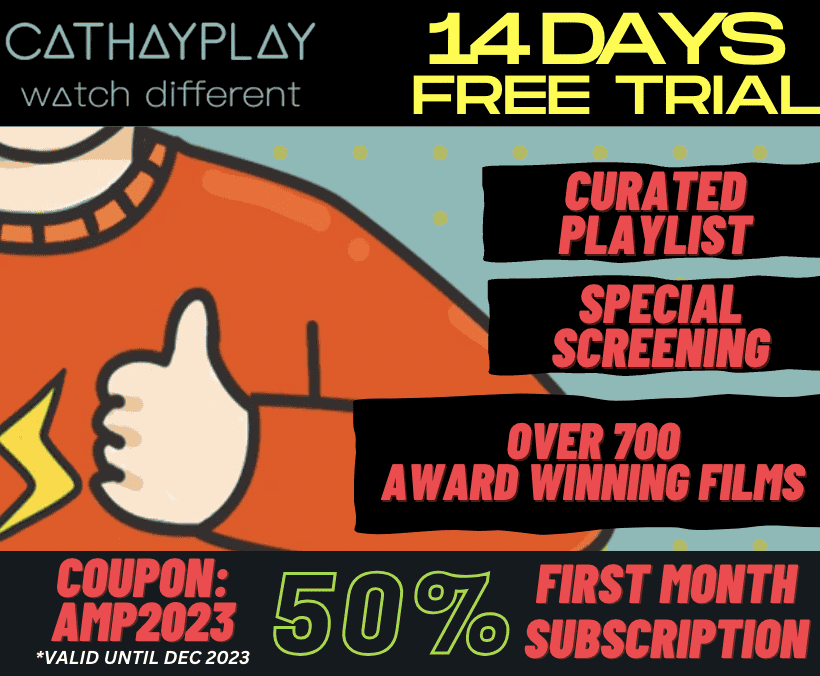あなたの映画はぴあフィルムフェスティバルでシネマファン賞を受賞しました。あなたはこの成功を誇りに思っていますか、そしてあなたはあなたの将来のキャリアにどのように影響すると思いますか?
ぴあフィルムフェスティバルにおいてルギンスキーのような作風は主流ではありません。
非実写であること、物語の異常性、風刺、執拗な皮肉など、これらは僕らの個性に違いありませんが、素直で常識的な若い感性を求める映画祭においては不利になるだろうという予想があった。
ナンセンスな作品という感想より他には得られないとも思った。
故、映画マニアから選出された外部の一般審査員が、ルギンスキーを評価してくれたこと、そして映画ファン賞を与えてくれたこと、これについて私はひどく安堵しましたし、何より感謝を思うばかりです。
残念ながら、受賞による私のキャリアに対する直接的な影響は良くも悪くもなく低調という様子でしょうか。カテゴライズの難しい作品は国内において歓迎されない向きがあるのやもしれない。
一方で、ぴあフィルムフェスティバルを経て、香港国際映画祭に作品が招待されたことによって、海外からの多数の好意的な反響を頂きました。それらは感想というよりも作品の分析であったり、海外にてルギンスキーを観る機会をどうにかして設けて欲しいというような求めであったり、私が予想していたものよりも具体的で熱烈な応援でした。彼らの声に応えるためにも、また私達の創作活動を続けていくためにも、ネットフリックスやアマゾンプライムでルギンスキーの配信を実現したいのですが、その方法が皆目解らない。只々、もどかしいです。
ルギンスキーの背後にあるインスピレーションは何でしたか?なぜこのかなりユニークな視覚的アプローチを選んだのですか?どうやってタイトルを思いついたのですか?
当初、私からジャン・ピエールへ「一緒に映画をやってくれ」と提案したことが制作のきっかけになりました。ともかくとして、ジャン・ピエールはコラージュ作家であり、つまりは基本の映像には静止画を用いる他ありません。
そこで私は『ラ・ジュテ』のようなフォトロマン形式であれば、彼のコラージュを何百枚も使用することで、映画として表現やれるのではないかと思い至りました。何をどうしても視覚的に通常の映画の体裁にはなりませんし、そもそも作品を完成させるための手順などについて私達は無頓着でした。どうにかなるだろうという浅慮の他なかった。改めて顧みると、馬鹿げていて無計画でした。
馬鹿げていて無計画で考えのない頭空っぽな二人だからこそ、無謀で自由な創作に臨めたのやもしれません。
タイトルに関して、近頃の日本映画の場合は、ポップ、キャッチー、わかりやすさを意識したそればかりというような印象があります。生意気やもしれませんが、こうした流行りをガキっぽくて野暮だなと思うのは、こちらの頭が旧い所為なのか。こんなハナシはどうでも構いませんが、今作ではLUGINSKYが一体誰なのかということを劇中では明示しておらず、つまりは登場人物ですらないポーランド系の名をタイトルとすること……このように如何にも熟考の末なのだと格好つけたいところですが、実際のところは思いつきでした。後になって、クールでディープなタイトルにしてやったぜと少しばかり自惚れていたんですが、日本人にはあまりにも馴染みがなかったようで、大概は「ルジンスカイですか?」と誤読されるばかりでした……
これらのさまざまな要素をすべて一緒に編集することはどれほど困難でしたか? 映画で使ったテクニックについてもう少し詳しく教えてください。ジャン・ピエール・フジとの協力についても詳しく教えてください。
「台詞に頼ることなく映像で以て物語を観客に伝えられない作品は稚拙である」と保守的な映画ファンに得意の顔で語られたのは一度や二度ではない。クソくらえだ。
ルギンスキーの制作において、私は映像によって物語を観客に把握させるという当たり前の工夫を意図的に抑制した。ジャン・ピエールのコラージュは複雑で不規則、色が溢れ、一見して理解やれるような代物ではない。加えて、「もう少し物語に沿った映像にしてくれ」と修正を指示する、すると彼は「任せろ」という頼もしい返事をくれる、けれども修正を加えられた映像は、更に複雑になり前衛めいたそれになるということが度々ありました。そこで彼の画を活かしながら映画として成立させるためには、通常の台詞の展開では儘ならないと考えを改めました。先ずミュージックビデオの手法に倣い、物語の具体的な表現を抑えて、イメージからイメージへと短く画を繋いでいくことに徹した。そして、たとえ映像と矛盾しようがどうだろうが台詞とモノローグによって物語を進行させるという方法を採用した。モノローグの文体を脚本のそれではなく小説の形式にしたのは奇異の程度が過ぎたやもしれないが、これは私自身が二十年間も小説を書き続けて日の目を見られなかった未練でもあって……ともかく、今作においては適した手段、判断だったと考えています。
ムーセッタが「普通の」人間であるのに、なぜディアマンには鹿の頭があり、バーマンにはパンサーの頭があるのですか?
常識的な作品にするのであれば、ムシェットを含む登場人物すべてを動物の顔にするべきだった。しかし私は創作においての常識に対して、抵抗しなければならないという無意識の決心があるようです。そのため、登場人物の顔を同じ何かで揃える必要を思わなかった。
また鹿男やバーマンの異常な精神状態や存在性を、生身の人間の表情で表現することは不可能だという考えもありました。
この映画は、金持ちと貧乏人の間の分裂に焦点を当てています。この件についてどう思いますか?
毎日のように私は自身に対して失望し後悔する。どうしてこうなったのかと。どうして際限なく不足を思い知るような情けない暮らしに在るのかと。文学や音楽の創作に明け暮れて悉く挫折した故だと自覚していても、惨めったらしく落ちぶれていくような気分が募る。畢竟、私はルサンチマンの塊になった。錆びだらけになった200ccのオートバイを労わるように走らせている隣を馬鹿でかい高級SUVが駆けていく。それを眺める度、けして届かない金持ち連中の日常に対して、彼らの所有や安寧に対して、卑屈な妬みや諦念、隔たりを覚えるようになった。そうした屈折した虚無感めいた感覚が少なからずルギンスキーの物語に影響しているやもしれません。
日本だけでなく世界中で貧富の格差について取り上げられるようになりましたが、確かなのは私自身が格差社会の最中に在り、ろくでもない身上である当事者だということ。けれども自身という当事者が問題提起や辛い苦しいといった事情を見せびらかすのは、タフガイ気取りの強がりやもしれませんが、手前のやり方ではありません。故、大袈裟で執拗な風刺や皮肉などを物語に散りばめることによって、私自身という存在も含めて、世界の組み立ての美化を徹底して否むというようなニヒリズムを反映させたつもりです。
Moucscettaは、貧しい人々は喫煙、飲酒、買い物、テレビの視聴、そしてセックスしかできないと述べています。この概念は映画全体で繰り返されています。これについて詳しく説明していただけますか?
LUGINSKYの世界、その体制下において大衆に許されている娯楽は「テレビとセックス、買い物、飲酒と喫煙」より他にない。
こうした設定を設けた理由のひとつは、高等市民と平民という階級制度の敷かれた管理社会、そこで生きる大衆は発展や進歩を望めず、習慣に伴う消費という単純な遊興に気晴らしを求めざるを得ない、そのメタファーとして用いました。メタファー?
また日本は宗教に対して否定的な面がありながら、どうしてなのか、セックスに対しての表現を伏せなければならないというような感覚、どこか二十世紀の因習的な気配があるようにも思える。
勤勉であること、平均的な了見の人間であること、冒険をしないこと、斯様な生き方や日常が一切であるというような硬直した世間に、私のような与太者は適応やれないし不服である。色恋を得られず欲求不満、しかしその不幸せを自覚しない潔癖で旧い道徳に憑かれた連中が、寄ってたかって奔放で自由な人間を謗るような光景を私は肯定しない。
「テレビとセックス、買い物、飲酒と喫煙」という彼らが殊に嫌うであろう言葉、行為を強調した裏面には、保守的で考えが硬直してしまっている連中への挑発と、一方でこの作品を面白がれる人々のオープンマインドな人間性、私と通じ合える人々との出会いを期待していたところがあります。
現在の映画業界についてどう思いますか?
映画業界について何も知りません。
映画業界というものがどうだろうがやりたいようにやるだけだ。
あなたは何かプロジェクトに取り組んでいますか、そしてあなたはこの実験的な道を続けますか?
現在、LUGINSKYの続編となる作品を制作中です。2022年の春頃には完成する予定です。
また、ぴあフィルムフェスティバルのPFFスカラシップに提出する自身の最終的な企画を整えている最中です。選考されるかどうかは解りません。ともかくとして、私はジャン・ピエールやLUGINSKYを制作した友人達と離れられない。彼らがこちらを見捨てない限り、どんなに銭がなくても、どうしようもない事情に陥っても、私が創作をやめることはない。他にやることもないしね。